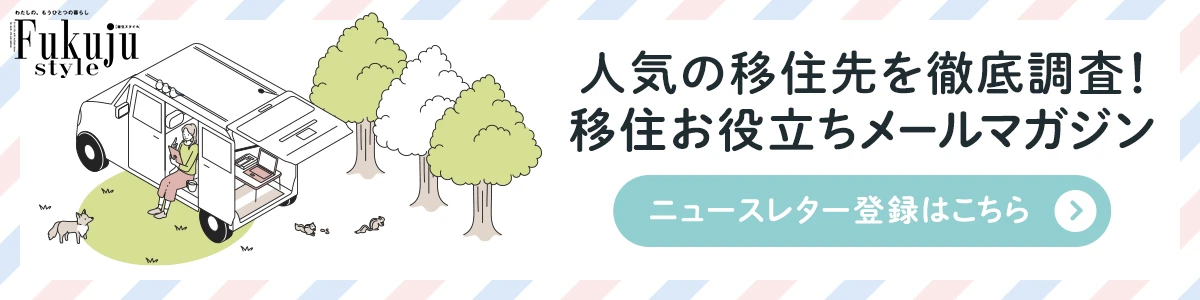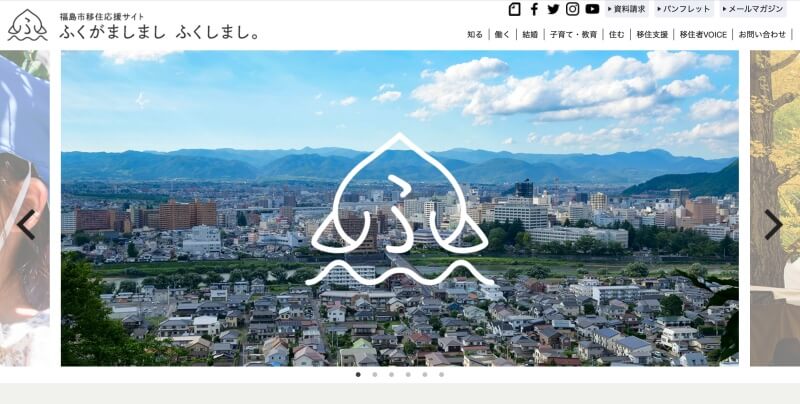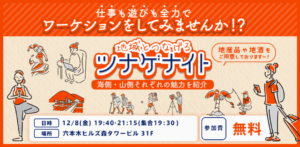二拠点生活は、都市と地方に拠点を持つ新しいライフスタイル。補助金を活用すれば初期費用を抑えて理想の暮らしが可能です。
この記事では、補助金の活用法や支援制度を紹介します。
二拠点生活とは?ライフスタイルの変化と背景


近年注目を集める二拠点生活は、都市と地方の両方に生活拠点を持ち、柔軟な働き方や豊かな暮らしを実現するライフスタイルです。テレワークの普及や働き方改革により、自然に囲まれた環境で心身を整えつつ、都市部でのキャリアを継続する「デュアルライフ」を選ぶ人が増えています。
また、地域との関わりを深めることで新たな「関係人口」が増え、これが地方創生にもつながっているのです。この記事では、こうしたライフスタイルや価値観の変化を踏まえて、理想的な二拠点生活をはじめるための基礎知識をわかりやすくご紹介します。
二拠点生活が注目される理由
テレワークの普及によって、場所にとらわれない働き方が広がっています。都市部の利便性を享受しながら、自然豊かな地方で暮らす二拠点生活は、仕事と暮らしのバランスを重視する人々から注目されています。
通勤時間の短縮やストレスの軽減など、生活の質を向上させるメリットも。また、企業でもリモートワーク制度の導入が進み、社員が柔軟に働ける環境を整える動きが広がっています。
デュアルライフがもたらす新しい価値
デュアルライフは、都市と地方の双方に拠点を持つことで多様な価値を創出するライフスタイルです。地域のイベントやボランティア活動に参加することで、地元住民との交流が生まれ、関係人口として地方創生に貢献できます。
また、異なる文化や自然環境に触れることで新たな発想が生まれ、仕事や暮らしの質を向上させる効果もあります。ライフステージに応じて拠点を使い分ける柔軟さが、現代の理想的な暮らし方として支持されているのです。
二拠点生活のメリット・デメリット
二拠点生活には、自然豊かな環境で心身をリフレッシュできることや、都市部と地方の両方で働ける柔軟な働き方を実現できるという大きなメリットがあります。テレワークや働き方改革が進む中、地方での生活費を抑えつつ、家族と過ごす時間の充実を選ぶ人も増えています。
一方で、拠点の数が増えると家賃や光熱費などの費用負担が増すほか、税金や年金などの手続きにも注意が必要です。
とくに、住民税や固定資産税が重複する場合や、社会保険の加入条件などは事前に確認しておく必要があります。
メリット:豊かな自然と多様な働き方
二拠点生活の最大のメリットは、自然豊かな環境で心身をリフレッシュしながら、都市部での仕事を継続できる点にあります。テレワークが普及したことで、地方でも都市と同じように業務を遂行できる環境が整いつつあります。
生活費が比較的安い地域を選べば、経済的な負担を軽減しながら、週末には自然の中でリラックスできるのも魅力です。家族と過ごす時間を増やし、趣味や地域活動にも取り組むことができるため、ワークライフバランスを重視する人々にとって理想的なライフスタイルといえるでしょう。
デメリット:費用・税金・年金などの注意点
一方で、二拠点生活には注意すべきデメリットもあります。まず、拠点が増えることで家賃や光熱費などの費用負担が大きくなり、予想以上にランニングコストが高くなるケースもあります。
また、住民票や税金、年金などの手続きが煩雑になりがちです。とくに、住民税をどちらの自治体に納めるのか、国民健康保険や年金の加入先については、事前によく確認しておきましょう。費用と制度の両面で計画を立てることが重要です。
二拠点生活にかかる費用
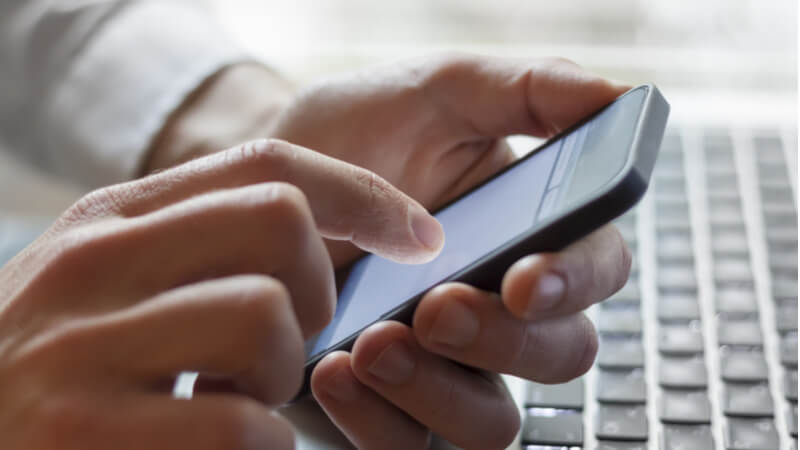
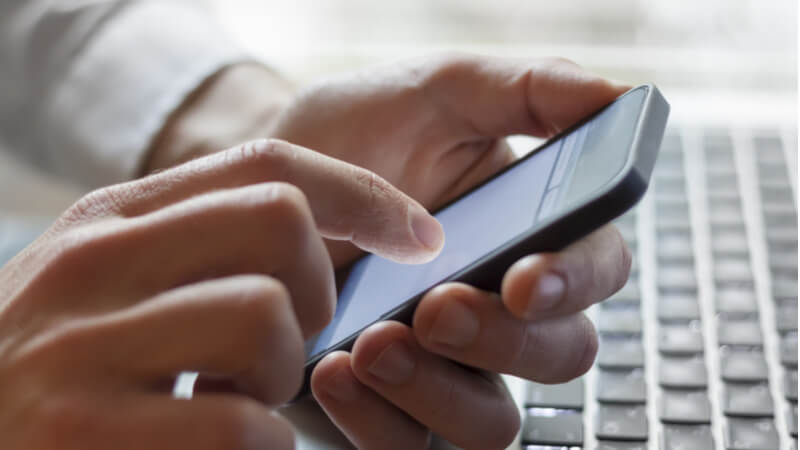
初期費用は賃貸契約の敷金・礼金や家具購入費などで30〜50万円が目安です。住宅を購入する場合は登記費用やローン手数料も必要です。
また、ランニングコストには家賃や光熱費・通信費・交通費などがかかり、拠点を2つ持つことで全体の負担が大きくなる傾向もあります。支出を抑えるには、家賃の安い地域を選ぶ、定額制通信サービスを利用する、移動回数を減らすなどの工夫が効果的です。
事前に費用シミュレーションを行い、無理のない資金計画を立ててください。
初期費用の内訳と目安
二拠点生活をはじめるにあたって発生する初期費用には、賃貸物件の場合、敷金・礼金・仲介手数料などの契約費用のほか、家具家電や生活用品の購入費が含まれます。これらを合わせると、地域や物件の条件にもよりますが、30〜50万円程度が目安となります。
住宅を購入する場合は、登記費用やローン事務手数料などの諸費用も発生するため、予算計画に余裕を持たせることが重要です。自治体の住宅取得補助やリフォーム支援制度を活用すれば、初期費用を抑えつつ理想の拠点を整えることができます。
ランニングコストを抑えるコツ
二拠点生活では、家賃や光熱費、通信費、交通費などのランニングコストが継続的にかかります。負担を減らすためには、家賃の安い地域を選ぶ、再生可能エネルギーを利用して光熱費を抑える、インターネットやモバイル回線を定額プランにまとめるなどの工夫が効果的です。
また、移動回数を減らすことで交通費も削減可能です。さらに、自治体によっては長期滞在者向けの住宅支援や交通費支援があるため、制度を活用して、無理のないコスト管理を行ってください。
二拠点生活で活用できる補助金・支援制度
二拠点生活を検討する際には、国や自治体が提供する補助金・支援制度を上手に活用することが重要です。とくに注目したいのが、国の「地方創生移住支援事業」です。
東京圏から地方に移住し、現地で就業またはテレワークを行う場合、単身で最大60万円、世帯で最大100万円の支援金を受け取ることができます。
さらに、自治体ごとに独自の支援制度として、住宅購入支援や空き家バンクの活用、移住体験施設の提供なども。これらを上手に組み合わせれば、初期費用を抑えて理想の暮らしをはじめやすくなります。なお、条件や申請時期は各自治体の公式サイトで必ず確認しましょう。
国の「地方創生移住支援事業」
国が実施する「地方創生移住支援事業」は、東京圏から地方へ移住し、現地で「就業」「起業」または「テレワーク」を行う人が対象となります。単身世帯は最大60万円、家族世帯は最大100万円の支援金の対象です。さらに子育て世帯向けへの加算金がある自治体もあります。
申請は移住先の自治体を通じて行うため、対象条件や手続きの流れを事前に確認しておくことが大切です。


自治体の支援例:住宅購入・空き家バンク・リモート支援
各自治体では、二拠点生活を後押しするために多彩な支援制度を展開しています。
たとえば、住宅購入費の一部を補助する制度や、空き家バンクを通じた低コスト物件の紹介、リモートワーク環境の整備支援などがあります。また、移住体験施設を提供しており、短期間のお試し滞在ができる地域も増加中です。
これらの支援を利用すれば、初期費用を抑えて生活をスムーズにはじめられるため、理想のデュアルライフも実現しやすくなります。










二拠点生活をはじめる前に知っておきたい注意点


二拠点生活をはじめる前には、行政手続きや社会保障制度について事前に確認しておくことが大切です。まず、住民票は滞在期間が長い拠点に置くのが原則です。どちらの自治体に住民税を納めるか、また国民健康保険や年金の加入先がどこになるかを確認しておきましょう。
拠点を分けることで、税金や保険料の計算が複雑になる場合もあります。さらに、補助金や支援制度を受ける際には、住民票の移動が条件となるケースが多いため、事前に自治体の要項を必ず確認してください。
制度や税制は毎年更新されるため、最新情報を公式サイトで確認し、安心して二拠点生活をはじめられるように準備を整えてください。
住民票の置き方と税金の扱い
二拠点生活を行う際、住民票は1つの自治体にしか置けない点に注意が必要です。原則として、1年のうち最も長く住む拠点を「主たる住所」として登録します。住民票の所在地が、住民税や国民健康保険料の納付先となるため、誤った登録は税金や保険料の計算に影響します。
どちらの拠点に主たる居住実態があるかを明確にし、自治体に相談しながら正しく手続きを行いましょう。
年金・保険など社会保障の注意点
二拠点生活では、勤務先の社会保険に加入している場合を除き、国民年金や国民健康保険の加入手続きを主たる拠点で行います。居住地を分けていると、郵送物の管理や納付手続きが煩雑になることがあるため、マイナポータルやオンライン申請を活用すると便利です。
また、扶養家族がいる場合は、世帯全体の保険料や年金記録にも影響が出ることもあるため、住所変更後はできるだけ早く関連する機関に届け出てください。
二拠点生活を成功に導く4つのステップ


二拠点生活の成功には明確な計画が必要です。ステップ1では目的を整理し、期間や拠点のバランスを明確にします。
次に、ステップ2として地域選定を行い、生活環境や支援制度の有無を比較検討しましょう。ステップ3で賃貸物件や空き家バンクを活用して理想の物件を探し、ステップ4では補助金や支援制度の申請手続きを進めます。
この4つのステップを踏むことで、費用や手続きの負担を抑えながら、自分に合った二拠点生活を計画的に実現することが可能です。
ステップ1:目的を明確にする
二拠点生活をはじめる前に最初に行うべきことは、自分がなぜこのライフスタイルを選びたいのかという目的を明確にすることです。仕事の効率化・家族との時間の確保・趣味や自然との触れ合いなど、目的によって最適な地域や期間、拠点の使い方は異なります。
目標がはっきりすれば、費用計画や物件選定、補助金活用の方向性も定まり、後悔のない選択につながります。
ステップ2〜4:地域選定・物件探し・支援制度活用
目的が定まったら、次に地域選定を行いましょう。気候や交通の利便性、支援制度の充実度を比較して、自分のライフスタイルに合ったエリアを選びます。その後、賃貸や空き家バンクを利用して物件を探し、居住環境や費用面を確認します。
最後に、国や自治体の補助金・支援制度を活用して初期費用を抑え、必要な手続きを進めましょう。これらのステップを踏むことで、計画的かつ安心して二拠点生活をはじめられます。


二拠点生活におすすめの自治体3選


ここからは、二拠点生活におすすめの自治体を紹介します。
都内からアクセスしやすい地域や、支援制度が充実している地域を厳選したので、ぜひ参考にしてください。
【静岡県】静岡市(しずおかし)
出典:静岡生活 いいねぇ。
東京から新幹線で約1時間の好立地にある静岡市は、海・山・川の3拍子が揃った自然に恵まれた町です。
少し足を伸ばせば大自然にすぐアクセスできるので、サーフィンやトレッキングなどの趣味を満喫したい人にもぴったり。
また、桜えびやしらす、新鮮なお刺身など、駿河湾の海の幸を存分に堪能できるのも大きな魅力。
移住希望者向けのお試し住宅や、市内のコワーキングスペースを利用できるお試しテレワークなどもあるので、二拠点目を持ったときの生活をシミュレーションすることができます。
さらに、移住に伴う就業や住まいに関する補助金のほか、新婚世帯向けの「結婚新生活スマイル補助金」など、金銭的な支援制度も充実。気になる方は、詳細をチェックしてみてください。


【栃木県】栃木市(とちぎし)
出典:とちぎで暮らそ|栃木市
車でも鉄道でも東京から約1時間でアクセスできる栃木市は、移住支援が充実している自治体のひとつ。
市内には、1泊2,000円、1ヶ月なら30,000円で利用できる移住体験施設があります。
一つは、安政3年に建てられた見世蔵と土蔵を活用した「IJUテラス 蔵人館」。カフェが併設されているため、地元の方々との交流を楽しむことができます。
もう一つは、栃木市中心部の県庁掘沿いに佇む一軒家「蔵の街やどかりの家」。昭和25年に建てられ、畳とお風呂を新調した以外は、ほとんどが当時のまま。古民家暮らしに憧れている人にはぴったりのお試し住宅です。
東京圏から栃木市に移住してテレワーク等をする人を対象にした補助金制度もあるので、ぜひ最新情報を確認してみてください。


【福島県】福島市(ふくしまし)
出典:ふくがましまし ふくしまし。
福島市は二拠点生活に適したほど良い田舎で、ここ数年で移住者の数がぐっと増えている人気の町。東京からは、新幹線で約1時間半ほどで行くことができます。
そんな福島市では令和4年度から、新たに「プレ移住サポート事業」を実施しています。
民泊施設に滞在しながら、スーパーで食材を買って調理したり、小学校や保育所を見学したりといったリアルな移住体験ができる。
これは、地元のスーパーで食材を購入して調理、就業体験や施設でのテレワーク、小学校や保育所の見学、先輩移住者との面談…など、何かしらの移住体験を行う際に、滞在する民泊やゲストハウスなどの利用料を補助する支援制度です(※2泊から)。
ひとりあたり最大で1泊3,000円の宿泊補助を受けられるので、二拠点目に福島市を検討するなら、利用しない手はありません。




補助金を活用して理想の二拠点生活を実現しましょう


この記事で紹介したように、二拠点生活は補助金や支援制度を上手に活用することで、経済的な負担を軽減しながら実現できます。国の移住支援金や自治体独自の住宅補助、空き家バンク制度などを組み合わせれば、初期費用を抑えながら、理想の暮らしをはじめることも可能です。
まずは、自分の目的やライフスタイルに合った地域を選び、補助金や支援制度の条件、申請方法を調べてみましょう。これらの制度を活用することで、無理のない範囲で快適なデュアルライフが実現できます。