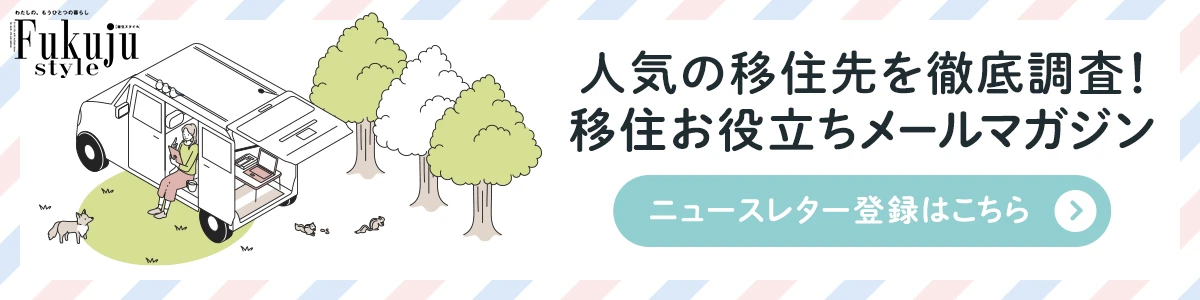地方移住をする前に確認しておきたい移住支援。移住支援は、国が提供しているものと、地方自治体ごとに独自で提供しているものに分かれており、その種類は実に様々です。
そこで、移住支援にはどんなものがあるのか、移住支援金は具体的にいくら貰えるのかを紹介します。代表的な制度をピックアップしたので、活用できそうな支援を探してみてください。
移住支援金制度の基礎知識
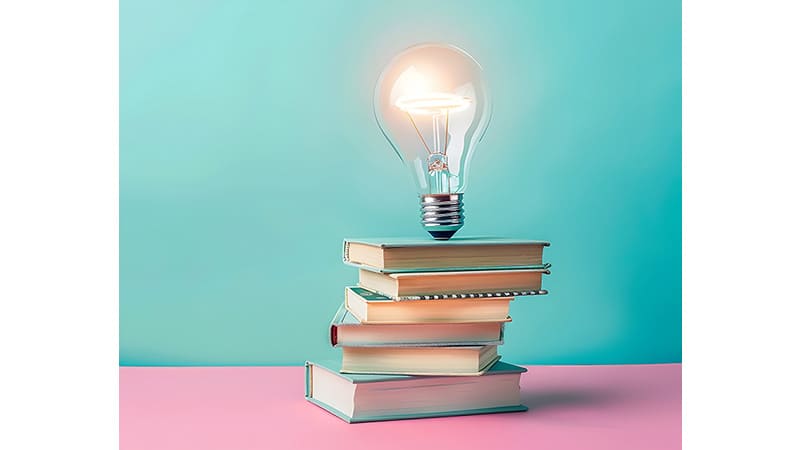
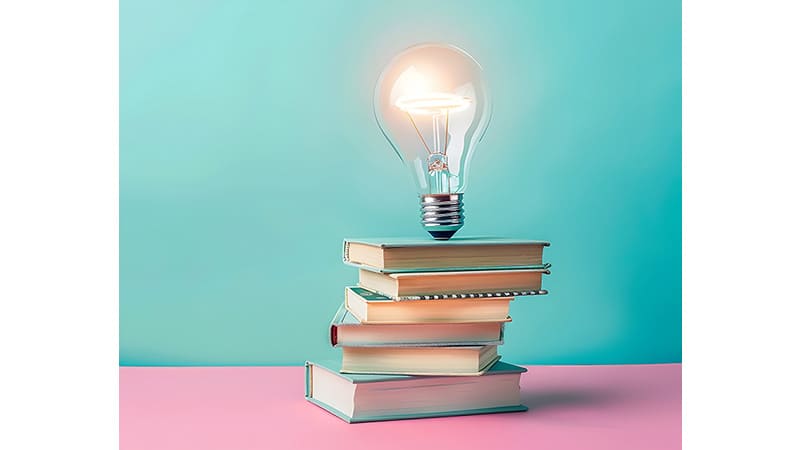
地方に住む前に抑えておきたい「移住支援金」制度。耳にしたことはあっても、その詳細までは知らない方も多いのではないでしょうか?
ここではそんな移住支援金について解説します。
移住支援金とは?金額・対象者
移住支援金制度は、2019年度から政府と地方自治体の共同で提供している取り組みです。
一定期間にわたり東京23区内に在住または東京圏(条件不利地域を除く)から23区内に通勤する人が、東京圏外に移住して起業や就業等を行う場合に、都道府県および市町村が移住支援金を支給しています。
なお、2021年度からは、移住前の仕事をテレワークで続ける人も給付対象となりました。
世帯移住で最大100万円、単身移住で最大60万円が受給され、国が半額、残りを移住先の都道府県と市町村が折半するかたちで運用されています。
さらに、移住先で地域課題の解決に関わる社会的事業を起業することで、最大200万円の支援金を追加で受け取ることができます。
2022年度からは、子育て世帯加算が新設。18歳未満の⼦どもを帯同して移住する場合、一人あたり最⼤100万円の⽀援金が追加支給されるようになりました。
アップデートを重ねたことで制度利用者が増加している移住支援金制度ですが、自治体によって金額や給付要件が異なったり、地方創生移住支援事業を実施していない自治体もあったりするため、必ず移住前に詳細を確認するようにしましょう。
移住支援金が受け取れるタイミングと注意点
移住支援金が支給されるのは、実は移住をした後! 自治体にもよりますが、基本的に移住・就職を経て、市町村への申請を行い、許可が下り次第支給という流れになります。
そのため、「引っ越し資金に充てよう!」 と考えている方は要注意。移住に必要な資金として支援金をカウントするのではなく、後から資金の一部が返ってくるような認識がベストです。
移住支援金申請の流れと要件
移住支援金を受け取るまでの大まかな流れと、受給対象者となる要件を解説します。まずは一度、各ステップを確認してみましょう。
【対象者】下記の両条件を満たす者
- 東京23区に在住、または東京圏(条件不利地域を除く)から東京23区へ通勤している者
- 移住直前の10年間で通算5年以上かつ直近1年以上在住または通勤している者
【対象条件】下記いずれかの条件を満たす者
- 移住先の地域で中小企業等へ就業
※移住支援金の対象として都道府県のマッチングサイトに掲載されている求人に就業すること。または、プロフェッショナル人材事業もしくは先導的人材マッチング事業を利用して就業すること。 - テレワークによる移住前の業務継続
- 市町村ごとの独自要件
- 地方創生起業支援事業を活用
※1年以内に起業支援金の交付決定を受けていること。
【申請条件】下記条件を満たしている者
- 移住支援金の申請が転入後1年以内であること
- 申請後5年以上継続して移住先市町村に居住する意思があること
- 東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県 ↩︎
- 一都三県の条件不利地域の市町村は以下。
東京都:檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
千葉県:館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、いすみ市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
神奈川県:山北町、真鶴町、清川村 ↩︎
対象条件を事前にクリアしておき、申請までの流れを理解して進めると吉です◎
全国の代表的な移住支援制度まとめ


移住支援制度のなかでも全国的に施行されている類似制度があります。ここでは、その代表的な支援例をまとめました。
住宅補助
主に外部から呼び込んだ移住者の定着や地域活性、空き家の活用を目的に実施される住宅補助。その種類は、土地や住宅の無償譲渡、家賃助成金の支給、家の購入・改修費の補助、情報基盤や太陽光パネルの設置補助と様々。
また、新婚・子育て世帯向けの定住促進奨励金を設けている自治体もあるため、単身者・家族連れに関わらず、幅広い層に該当する支援が見つかるはずです。


子育て支援
親子で移住する場合に気になる子育て支援。多くの地方自治体では、働く世代と未来を担う子どもたちが親子揃って移住してくることを奨励しています。
子育て支援では主に、高校生以下の子どもの医療費無償化や誕生祝い金の支給、給食費の支援、一時預かりサービス、おむつや粉ミルクなどの購入費補助・クーポン支給など新生児から幼児向けを中心とした助成が豊富です。


起業・就業支援
移住の際に困る職探し。どんな企業があるかも分からず、相談先も見つからないという方もいるかもしれません。そんな時に役立つのが起業・就業支援です。
地方自治体で起業をしたいと考える方に、社会性や事業性、その土地での必要性などを鑑み、一定の貢献度が認められた際には起業支援金が貰える場合があります。起業にまつわる経費の一部が助成されることが多く、自治体ごとに割合も異なるようです。
また、自治体が指定する企業マッチングサイトの求人に応募・就職し、移住を行うと就業支援金を貰えることも。人手不足解消のために、就業支援を手厚く行っている自治体もあるので、まずは一度確認してみましょう。
テレワーク支援
就業支援と近いものに、テレワーク支援があります。これは移住先に拠点を移しつつ、移住前の仕事をテレワークで続ける場合に一定の支援金を受け取れる制度です。
転職をせずに、支援金を貰いながら移住が叶うとあって、活用する人も増加傾向にある注目の支援となっています。


通勤・通学支援
働く世代と学生世代の双方に利点がある、通勤・通学支援。一定の範囲内で通勤・通学を行う場合に、その交通費の一部を助成金として受け取ることができます。
新幹線などの高速列車に適用される自治体もあるため、県外への通勤・通学を行う方にはぜひ利用をおすすめしたい支援です。
移住支援の活用で不安を解消!
移住をする際に金銭面の不安はつきものです。そんな中でも、移住支援金を賢く利用することで、困りごとを少しずつ解消していけるはず!
移住先となる自治体がどんな支援を行っているのか、自身が受給要件を満たす対象者であるのかをしっかりと確認し、期限を守って申請しましょう。