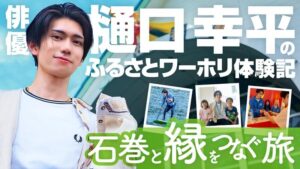ここ数年で知名度の増した「地域おこし協力隊」。地域おこし協力隊を簡単に説明すると、地方の市町村に移り住み、ある程度の収入を得つつ、地元の人々と密接に交流しながら活動できる制度のことです。
しかし「地域おこし協力隊という名前は聞いたことがあるけれど、そもそもどこで募集しているのかもわからない」といった人も少なくないでしょう。この記事で、地域おこし協力隊の制度概要やよくあるQ&A、頻繁に隊員を募集している自治体まで見ていきましょう。
地域おこし協力隊とは?


「地方に移住して、地元の人々と交流しつつ地域の一員として活躍したい!」
「移住を機に、これまでと異なる新たな仕事に挑戦してみたい」
「田舎ならではの温かい近所付き合いに憧れがある」
上記に当てはまる人にぴったりなのが、地域おこし協力隊です。
ただ、地域おこし協力隊と聞くと、過疎地域を盛り上げる人というイメージを持つ人が多いかもしれません。しかし、実態はもっと複雑で、それぞれの赴任先によってずいぶんイメージが異なります。
まずは地域おこし協力隊制度の基本情報を押さえておきましょう。
総務省が始めた地方活発化のための制度
地域おこし協力隊とは、総務省が推進する地方活性化の取り組みのひとつです。町おこし協力隊のような表現で呼ばれることもあり、総務省の公式サイトでは以下のように定義しています。
「都市地域から過疎地域等の条件不利地域に住民票を異動し、地域ブランドや地場産品の開発・販売・PR等の地域おこし支援や、農林水産業への従事、住民支援などの「地域協力活動」を行いながら、その地域への定住・定着を図る取組」
出典:地域おこし協力隊|総務省
この事業の基本的な目的は、都市地域から過疎地域など、人口が少ない地域に人を移住させることで、その地域への定住・定着を図ることです。
また、定住・定着を支援するために、地域おこし協力隊員にはそれぞれの地域の課題解決に向けた取り組みがミッションとして与えられます。これを「地域協力活動」と言います。
ボランティアではないため、地域協力活動の対価として給料が支給されるほか、任期中の住宅補助や必要経費に対する費用が支払われます。
令和8年に10,000人まで増やすことが目標
地域おこし協力隊の歴史は意外にも古く、2009年度から始まりました。初年度は89人しかいませんでしたが、2014年度には1,000人を超え、2021年度には6,000人を突破しています。
2023年度の地域おこし協力隊の隊員数は7,200人。政府は隊員数を令和8年に10,000人まで増やすことを目標としています。
また、活動地域を超えて日本全国の地域おこし協力隊員を支援する全国ネットワークも設立され、現役隊員や卒業後の隊員を支援する取り組みがなされています。
参考:令和5年度の地域おこし協力隊の隊員数等について|総務省
地域おこし協力隊にまつわるQ&A


地域おこし協力隊の制度について知ったところで、続いてはより詳しい地域おこし協力隊の内容について見ていきましょう。
ここからは、地域おこし協力隊にまつわるQ&Aもチェックしてみてくださいね。
給料はどこから出ている?
地域おこし協力隊の給料は、通常各自治体の行政機関から各隊員に支払われます。この財源になっているのは、各自治体が国から受け取る特別交付税です。
隊員一人当たりに支給される特別交付税の上限は令和6年度現在520万円です。この中には、隊員の月給のほか、活動経費や住宅補助に関する費用なども含まれています。
なお、自治体によって地域おこし協力隊との関係性が異なります。ある自治体では、自治体と隊員の間に雇用関係がある場合があります。一方で、隊員は個人事業主であり、自治体は地域おこし協力隊の業務を委託するという関係性もあります。
自治体との雇用関係がない場合には、隊員が独自で各種保険や国民年金に加入したり、確定申告をしたりしなければならないため、自治体との関係性も事前に確認しておきましょう。
参考:地域おこし協力隊|総務省
ボーナスはある?
地域おこし協力隊に関する交付税の上限は決まっているものの、全ての地域おこし協力隊員が同じ待遇を受けているわけではありません。月給の額は赴任先の自治体によって異なり、住宅補助などの活動経費の上限も異なります。
そのため、自治体によってはボーナスが支給されるところもある一方で、支給されない場合もあります。
月額給料やボーナスの支給有無に関しては、地域おこし協力隊の募集要項に記載があるため、その内容をよく確認するようにしましょう。


年齢制限はある?
地域おこし協力隊の応募に年齢制限は設けられていません。基本的に18歳以上であれば応募可能です。
そのため、大学を卒業したばかりの20代から50代以上のベテランの社会人まで、さまざまな年齢の人たちが地域おこし協力隊として各自治体に赴任しています。
しかし、募集内容によっては特殊な経験や技能が求められる場合もあり、必ずしも誰もが応募できるわけではありません。募集ごとに年齢制限の有無・内容は異なるため、応募前に確認してみましょう。
任期の上限や下限はある?
任期はおおむね1年以上3年以内です。同じ自治体で3年以上地域おこし協力隊を続けることはできません。
また、基本的には1年ごとの更新となっており、隊員の意向を確認のうえ最大3年まで地域おこし協力隊として活動することができる仕組みになっています。
心身の問題や活動地域にうまく馴染めないなど、さまざまな問題が生じて任期途中で隊員を辞めてしまう人もいます。
参考:地域おこし協力隊|総務省


地域おこし協力隊のミッションは何?
地域おこし協力隊のミッションは自治体によってさまざまです。
基本的には、各自治体の地域課題を解決するためのミッションがあらかじめ指定されています。ミッションの内容によって募集内容や要件は異なります。
ミッションの例として、自治体の空き家問題の対策や移住促進、自治体のPRや伝統工芸・農業の後継者育成などが挙げられます。また、自治体によっては特にミッションを設けていないフリーミッション型もあります。
地域おこし協力隊に応募する際には、そのミッションは自分が対応できるものなのかどうかを考慮することが重要です。
企業連携型の地域おこし協力隊とは?
地域おこし協力隊の中には、特定の企業と連携しながらミッションに従事する場合があります。そのような地域おこし協力隊の活動を企業連携型と言います。
企業連携型の場合、活動する場所が企業の事務所であったり、場合によっては企業の社員になったりと、通常の地域おこし協力隊とは異なる動きになることがあります。
企業連携型のメリットは、個人ではなく企業としてミッションに取り組めるため、大きな動きができることや、信頼を得やすいことです。
一方、企業としての取り組みになることが多いため、自分の一存で意思決定することができないというデメリットもあります。
その後(任期終了後)はどうなる?
最大3年の任期の後、地域おこし協力隊員はどのようになるのでしょうか。
まず、募集時点で、任期終了後も赴任地域に定住するという条件があります。そのため、基本的にはその地域に住み続けることが前提です。
しかし、状況によっては定住し続けることが難しい場合もあるため、任期終了後は赴任した地域を離れてしまう隊員もいます。
任期終了後の定住ができるかどうかは、そこで仕事を続けられるかどうかにかかっています。隊員によっては自分で起業する場合もあり、地域の企業に就職する場合も。また、赴任先の自治体の議員になったという例もあります。
任期後に赴任先で起業をする場合には、最大100万円の起業支援補助金が受けられることもあります。
いずれにしても、その地域に定住できるためには、任期内に地域の人たちとしっかり信頼関係を築き、任期終了後のイメージを描きながら活動することが大切です。
特別交付税措置とは?
特別交付税措置とは、地域おこし協力隊にまつわる、国から地方自治体への補助金の支払われ方に関する話です。隊員視点では直接関係がなく、メリットもデメリットもありません。
一般的に、国から地方自治体に対しての財政支援は「地方交付税」として支払われる形が主流です。この地方交付税は「普通交付税」と「特別交付税」の2種類に分かれています。
そして、地域おこし協力隊にまつわる補助金の多くは、後者の特別交付税として支払われています。
参考:自治体向けQ&A(「地域おこし協力隊の受入れに関する手引き(第3版)」より)
地域おこし協力隊の問題やトラブルって?
地域おこし協力隊に興味はあるものの、全然知らない土地に飛び込んでいくのは勇気のいることです。これまでの常識が通用しないこともあり、それが原因で問題やトラブルを招いてしまう場合もあります。
実際のトラブル例をもとに、トラブルを回避するにはどうするべきなのかを考えてみましょう。
トラブル例
一つ目のトラブル例は、赴任先の活性化のためという理由で、都会での活動が中心となったことで、地域住民との関係が悪化したこと。これは、地域住民との交流機会が少なくなり、隊員に対する感情が悪くなってしまった例です。
もう一つのトラブル例は、イベントを実施するにあたって、地域住民と揉めてしまったこと。隊員のスピード感に地域住民がついていくことができず、関係性が悪化したという事例です。
トラブルを回避するにはどうすべき?
これら二つのトラブル例に共通することは、地域住民の視点が欠けていたということです。地域おこし協力隊としては「この地域をなんとか自分の力で変えたい」と強い思いで臨んでも、独りよがりになってしまうことがあります。
また、都会で仕事をしていたときの常識を持ち込んでしまうと、地域住民がついていけないこともあります。都会でバリバリ仕事をしてきた隊員にとっては、「なぜそんなこともできないの?」と憤ってしまうことがあるかもしれません。
しかし、それぞれの地域にはそれぞれの歴史があり、そこに住む人たちのプライドがあります。それを無視して、よそからやってきた隊員が無理矢理何かを変えてやろうと思っても、うまくいきません。
大切なことは、地域住民とのコミュニケーションです。お互いに理解を深め、助け合いの精神が生まれれば、地域にとっても隊員にとってもいい仕事ができるはずです。


募集サイトはどこ?
まず、全国でどのような地域おこし協力隊の求人があるのかを確認しましょう。
全国の求人情報を載せているのは、JOINやSMOUTといった地方移住に関する情報発信をしているサイトです。これらのサイトには募集中の地域おこし協力隊情報が載せられています。
また、地域おこし協力隊を募集するのは各自治体なので、各自治体のホームページにも地域おこし協力隊の求人情報が載っている場合もあります。
地域おこし協力隊は年間を通してさまざまな自治体が求人を出しています。現在は求人を出していない自治体でも、近い将来に求人を出す可能性がある場合もあるため、自分が気になる自治体がある場合には、直接問い合わせしてみるのも一つの方法です。


地域おこし協力隊を積極的に迎え入れているおすすめ自治体5選


ここからは地域おこし協力隊の受け入れに積極的な、おすすめの自治体を紹介します。
現在、日本全国で多くの自治体でが地域おこし協力隊を積極的に受け入れています。また、地域おこし協力隊と一口に言っても、なかには特徴的な募集も。
ここでは、特徴のある募集を行っている自治体を5つご紹介します。
兵庫県篠山市(しのやまし)
出典:丹波篠山地域おこし協力隊
兵庫県篠山市は、京阪神地域から1時間の里山地域です。
この自治体では、これまでに32名の地域おこし協力隊が活動しており、受け入れに積極的な自治体であると言えます。
ミッションはさまざまですが、この自治体では「テーマ型」の採用枠を設けています。テーマ型とは、自治体が設けたテーマに対して活動をするというものです。自治体が設けたテーマは「丹波篠山の誇れる取り組みを活用した観光振興」です。
このように、取り組み内容ではなくテーマが決まっており、テーマに沿った具体的な活動を地域おこし協力隊が考え、取り組むという地域おこし協力隊もあります。
鹿児島県日置市(ひおきし)
出典:地域おこし協力隊|鹿児島県日置市
鹿児島県日置市では、地域おこし協力隊の活動としては珍しい求人があります。その内容は、脱炭素事業推進です。
日置市は環境省が選定する「脱炭素先行地域」に選ばれていることから、この事業を推進していくための原動力として、地域おこし協力隊制度が使われています。そのため、募集要件がやや高めなのが特徴です。
行政と協業をしながら地域を動かしていくことに興味がある方にとっては、魅力的な地域活動であると言えるでしょう。
群馬県桐生市新里町(きりゅうししんさとちょう)
出典:桐生市地域おこし協力隊|桐生市ホームページ
群馬県桐生市新里町では、既存の農産物直売所を盛り上げることをミッションとした、地域おこし協力隊の募集が行われています。
地域おこし協力隊というと、「新規事業を興す」イメージがありますが、このような既存施設の活性化に従事するミッションもあります。
また、この地域の特徴は東京の浅草駅から乗り換え一回という利便性の良さも◎都会から地方移住を希望する方にとって、便利な都会に比較的近い立地条件というのは魅力的なのではないでしょうか。
このように、地域おこし協力隊の中には都会へのアクセスが比較的良い自治体もありますので、田舎暮らしと都会の生活を両立したいと思う方は、そのような自治体を探してみてもいいかもしれません。
北海道羅臼町(らうすちょう)
出典:羅臼町地域おこし協力隊の募集について| 羅臼町 世界自然遺産・知床の町
北海道は全国の中でも地域おこし協力隊を積極的に受け入れている自治体です。
北海道の中の各市町村が地域おこし協力隊制度を上手に活用しています。ミッション内容は農業分野から観光分野とさまざまです。
羅臼町で募集している地域おこし協力隊のミッションはやや特殊で、地域スポーツ振興に関する事業となっています。
また、この募集の特徴の一つは、自治体の会計年度任用職員として任用されることです。社会保険への加入や昇給の可能性があるのは魅力的です。
新潟県(にいがたけん)
出典:令和6年度ニイガタコラボレーターズ(新潟県地域おこし協力隊)募集|新潟県ホームページ
こちらは地域おこし協力隊としては珍しい、県としての地域おこし協力隊募集です。さらに、この地域おこし協力隊は起業型地域おこし協力隊で、林業に関する新しいビジネスを興すことを目的としています。
縁もゆかりもない場所で、いきなり起業をするのは難しいですが、起業家のメンターが伴走したり、起業研修が予定されていたりと、手厚いサポートがあるのも特徴的です。
「いつか起業したい」と思っていて、林業関係に興味がある方にとってはぴったりの地域おこし協力隊だと言えるでしょう。
地域おこし協力隊として自分が貢献できる自治体を選ぼう!


現在、全国の自治体が地域おこし協力隊の人材募集を積極的に行っています。地方移住を検討している人にとっては、地域おこし協力隊の制度を活用することで、給料面や住宅面の補助を受けられるため、とても便利な制度であると言えるでしょう。
しかし、地域おこし協力隊には貴重な税金が使われていることを忘れてはなりません。そして、自分を受け入れてくれている地域に対して、自分はどのようなことが貢献できるのかを考える必要があります。
自分が思い入れのある自治体に、地域おこし協力隊として移住したいという気持ちはとても大切なこと。その一方で、自分はその地域のために何ができるのか、という視点を持ち続けることも非常に重要です。
地域おこし協力隊に興味を持ったら、まず「自分ができること」について考えてみてください。
そうすれば、自分の経験や才能を活かすことができる自治体に巡り会い、自分にとっても地域にとっても、プラスになる活動をすることができるでしょう。







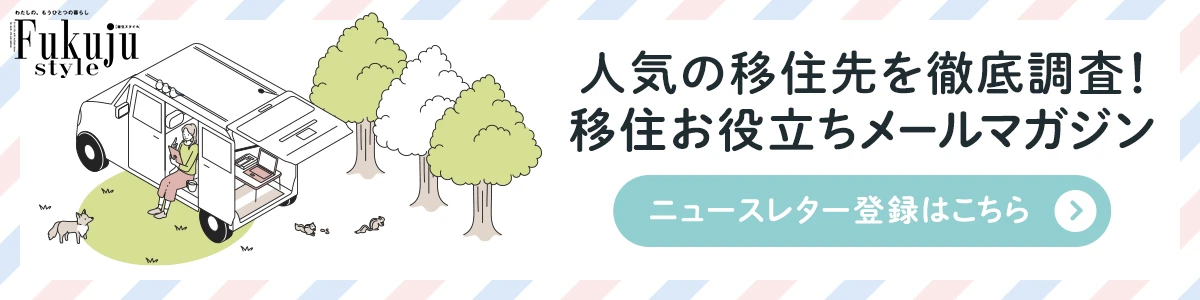
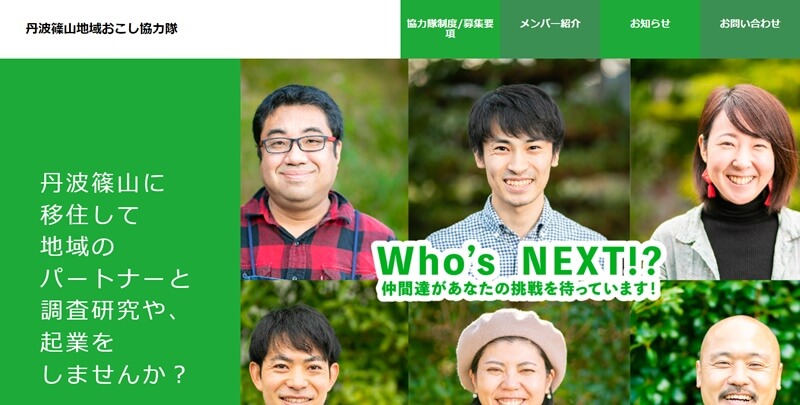



募集-新潟県ホームページ-1.jpg)