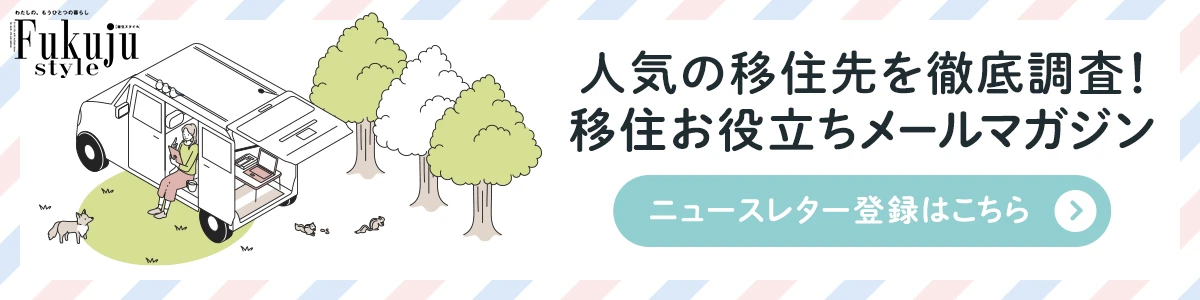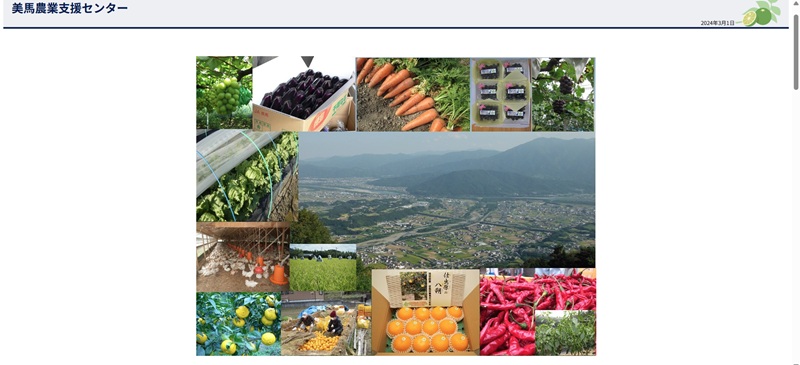都会からの移住にあたって、多くの方が憧れるのが“農業”。自給自足とまではいかずとも、農業を生業にして、自然とともに生きる新しいライフスタイルをはじめたい方は多いのではないでしょうか。
ここでは、移住を機に農業をはじめる方法や活用できる支援金、農家へのサポートが充実したおすすめ市町村を詳しく紹介します。
移住して農業を始めたい方へ|活用できる支援金・補助金制度


「田舎や地方に移住して新しい生活をはじめたい」と考えたとき、最初に思いつくのが“農業”ではないでしょうか?
都会の喧噪に疲れ、自然に触れながら穏やかに暮らしたいと願う瞬間は誰にでもあるでしょう。「自給自足までは難しくとも、農業を生業にしてみたい…」と憧れるものの、夢物語だと諦めている方も多いはず。
しかし最近では、地方創生の一環として、国や自治体が移住を推進するための支援制度を充実させています。
そのなかには農業にまつわる支援金もあり、一昔前よりも、移住して農家となるまでのハードルは劇的に下がりました。今や田舎&地方移住で農家暮らしをはじめることは、単なる憧れではなく現実的な選択肢です。
まずは、移住で農家暮らしをはじめるに当たって、農業関係の支援金にはどのようなものが存在するのか見ていきましょう。支援金の種類は多岐に渡るが、代表的なのは以下の4つです。
- 農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)
- 青年等就農資金
- 農業近代化支援金
- 移住支援金
農業次世代人材投資資金(将来の担い手を支援)
これから本格的に農家となりたい若者(原則49歳以下)を支援してくれる制度で、就農前をサポートしてくれる「準備型」と、実際に就農した直後の助けとなる「経営開始型」が存在します。
農業次世代人材投資資金とは、次世代を担う農業者となることを志向する者に対し、就農前の研修を後押しする資金(準備型)及び就農直後の経営確立を支援する資金(経営開始型)を交付する支援金のこと。
出典:農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金):農林水産省
過去には「青年就農給付金」の名前で運用されていました。
受け取れる金額など、それぞれの概要は以下の通りです。
【農業次世代人材投資資金(旧青年就農給付金)の概要】
| 準備型 | 経営開始型 | |
|---|---|---|
| 支援金額 | 12.5万円/月(150万円/年) | 12.5万円/月(150万円/年) |
| 期間 | 最長2年間 | 最長3年間 |
| 想定対象 | 就農に向けて必要な技術等を習得する研修期間中の研修生 | 次世代を担う農業者となることを目指し、新たに経営を開始する方 |
今から農業の勉強をしたい方でも対象となるのが嬉しいポイント。しかも、給付金であるため返還する義務もありません。農家移住を目指す方にとって心強い制度となるでしょう。
なお、実際に受給対象と認定されるには細かな条件があるため、まずは都道府県や市町村に問い合わせる形となります。
青年等就農資金
無利子かつ長期にお金を借りられる制度で、借入限度額は通常3,700万円、償還期限は17年。手元の資金が心もとない方であっても、大規模な農業をはじめられます。
農地の改良や農業機械の購入など認められる使途も幅広く、重宝するでしょう。
新たに農業経営を営もうとする青年等に対し、農業経営を開始するために必要な資金を長期、無利子で貸し付ける青年等就農資金により支援します。
出典:新規就農者向けの無利子資金制度について:農林水産省
18歳以上45歳未満の青年や、65歳未満のすでに知識や技能を有するものが対象となります。
こちらも農業次世代人材投資資金と同様に、借り入れに当たっては事前に都道府県や市町村などに相談する必要があります。
農業近代化支援金
青年等就農資金がこれから農業をはじめる方を想定しているのに対して、こちらはすでに農業を営むものが対象となります。
農業近代化資金とは、「意欲ある農業者等が経営改善を図るのに必要な長期かつ低利の資金」を借り入れられる制度のこと。
出典:農業近代化資金:農林水産省
金利は2.00%、償還期限は最長20年。個人の場合、通常1,800万円まで借り入れ可能です。
移住して農業を開始したのち、将来的に役立つこともあるでしょう。いざというときのセーフティーネットとして覚えておきたいですね。
移住支援金
移住支援金は、主に東京23区で暮らしていた方が、地方で農家暮らしをはじめたいときに対象となります。
移住支援金とは、東京23区に在住または通勤する方が、東京圏外へ移住し、起業や就業等を行う方に、都道府県・市町村が共同で交付金を支給する事業のこと。
出典:起業支援金・移住支援金 – 地方創生
制度の概要は以下の通りです。
【移住支援金の概要】
| 対象 | 移住直前の10年間で、通算5年以上かつ直近1年以上、東京23区内に在住もしくは通勤していた方 |
| 金額 | 100万円(単身は60万円) |
| 認められる移住先 | 一部例外を除き東京圏外 |
| 条件 | ・移住先の中小企業への就職 ・テレワークによる移住前の業務の継続 ・移住先で社会的起業などを実施 のいずれかを満たすこと。 |
農業の場合、自治体のマッチングサイトを活用して移住支援金の対象となる求人を探し、応募する形が基本です。
農業移住を実現するまでの3ステップ


次に、移住先で農家として生計を立てていくまでの流れを見てみましょう。
STEP1:「独立」か「就職」か、働き方を決める
まず行うべきは、ゼロから農家として起業したいのか、既存の農家に就職したいのか決めることが大切です。「農業次世代人材投資資金」が新規就農を想定しているように、起業か就職かで受け取れる支援金も変わってきます。
ゼロから農家として起業する
自分で農地を取得し、自分の好きな作物を育て、自分の責任で農業を営む。ひとりの農家として独立できるのがゼロから起業する方法です。「農業次世代人材投資資金」を受け取れるため、金銭面でもメリットが大きいのがポイント。
と言っても、完全な初心者が移住後すぐに独立農家となるのは現実的ではありません。
作物を育てるためのノウハウはもちろん、どのような農業機械が必要なのか、そもそも農地を取得できるのかなど、わからないことだらけでしょう。
農業大学校に通い知識を身につけるか、(独立を前提に)既存の農家に教えを請うか。いずれにせよ、農地の取得に関する打ち合わせや支援金の相談も兼ねて、自治体との密なコミュニケーションが必要となります。
既存の農家に就農する
独立起業を目指すよりも、よりハードルの低い形で農業をはじめられるのが、既存の農家への就職です。
農業以外の仕事をはじめる場合と同じように、求人を探して応募するだけでOK。採用され、移住して実際に就職した後は、その日から農家として暮らしていけます。まだ何の知識もない方も安心して就農できるでしょう。
加えて、移住支援金の対象となる求人に絞って検索することで、最大100万円の一時金も受け取れます。やり方次第では、引越し費用をそのままペイすることも可能です。
いきなり起業か就職かといわれても、なかなか判断ができないかもしれません。その場合は「自分の理想とする農家の形」だけ決めておき、後述するステップで、実際に農家の方や自治体担当者と相談してみるのもおすすめです。
STEP2:希望の条件から移住先候補を探す
起業か就職かのイメージがおぼろげにでも決まったなら、次は住んでみたいエリアを決めていきましょう。移住では、自分にとって理想的な住環境を見つけることも大切です。
「マリンスポーツもしたいから海の見える地域」「穏やかに暮らせそうな島が良い」と言ったように、日本地図を見ながら大まかに住んでみたいエリアを決めましょう。
もちろん、「みかんが育ててみたいから和歌山県!」といったように、農業を主眼に置いてエリアを決めても良いです。
おおよそのエリアが決まった後は、範囲内の自治体ページをチェックしていきましょう。自分が活用できそうな支援金や求人を確認すれば、これまでよりも移住がグッと身近になったように感じられるはずです。
STEP3:農業体験やインターンで適性を見極める
最後のステップは、希望のエリア内で農業にまつわる体験&インターンシップ施策を探して参加すること。
実際に自治体担当者や求人企業に連絡を取り、具体的な条件を確認したうえで、日程を決めましょう。当日に現地を訪れ農業体験を行えば、夢の農家暮らしはすぐそこです。
体験参加後は、担当者と今後の移住について話を進めていくのみ。活用できる制度など、気になる疑問点は移住前に積極的に質問してみましょう。


【2025年最新】農業移住におすすめの自治体10選!支援制度で比較


ここからは、農家としての移住におすすめな自治体を紹介します。今回は無料の農業体験が行えたり、自治体独自の補助金が存在したりと、移住支援が充実している地域を厳選しました。
徳島県美馬市
出典:美馬農業支援センター
まず紹介するのは、大自然のなかで農家として暮らしたい方にぴったりの移住先、徳島県美馬市。
県土総面積の8割が森林と緑豊かな土地で、山が多く、傾斜の強いエリアもあることで有名です。この傾斜を活かしたまま農業を行う営みは、「にし阿波の傾斜地農耕システム」として世界農業遺産に登録されています。
生産技術や経営管理などに対する支援を通じ、当地域の特色を活かした産地の育成をはじめ、産地を支える多様な担い手の育成、さらには地域の農産資源を活かした地域の活性化に向け、関係機関と連携を図りながら、計画的かつ効果的な普及指導活動を展開しています。
茨城県八千代町
出典:地域おこし協力隊|Re:BARAKI
「白菜の生産量日本一」を誇るのが、茨城県八千代町。県内の西側にあり、家々の間には畑や田んぼがたくさん存在する、小さくのどかな町です。
茨城県は県全体で70名以上の地域おこし協力隊員を受け入れるなど、移住者を積極的に迎え入れています。八千代町でも、地域おこし協力隊として梨を育ててみたい方を募集中です。
イチゴ農園の「ファーム八千代」でイチゴ狩り体験ができるなど、その時々で利用できるツアーはさまざま。まずは町の産業振興課農政係に問い合わせてみましょう。
千葉県佐倉市
出典:佐倉市で新たに農業を始めたい方へ|佐倉市
千葉県北部、東京都心から40kmとアクセスの良い距離に位置するのが佐倉市。年間平均気温が15度ほどと温暖で、農作物を育てやすい都市です。
佐倉市では新規就農者向けに独自の支援事業を行っており、新規就農に必要な経費(農業機器や資材の購入など)について、最大30万円(1/2の負担率)まで補助してくれます。
そのほか、農家連合との顔つなぎも行ってくれるなど、自治体が積極的に就農サポートを推進。移住後に農家として独り立ちするまで、担当者と二人三脚で歩んでいけるでしょう。
北海道新ひだか町
出典:新ひだか町新規就農情報サイト
移住先として高い人気を誇るのが北海道。雄大な大地のもとで、のびのびと暮らしてみたい方は多いのではないでしょうか。今回紹介するのは、北海道の南側、日高郡に位置する新ひだか町です。
新ひだか町は、北海道のなかでは比較的温暖で雪が少ない地域。農業も盛んで、特にミニトマトは道内でトップクラスの生産量を誇ります。
支援策も充実しており、農業実験センターにより新規就農希望者が研修を受けられるほか、特定の条件に当てはまれば月額最大21万円までの独自支援金も給付されます。まずは、自治体担当者と話を進めてみてはいかがでしょうか。
長野県飯山市
出典:農村定住支援住宅|飯山市
「現在は手元の資金が心もとないが、農家としての移住に興味がある…」そんな方にぴったりなのが、長野県飯山市です。
映画「阿弥陀堂だより」の舞台としても有名なこの土地では、移住に伴って農業に取り組みつつ、飯山市への定住を目指す方を対象に住宅支援を行っています。
最大3年間、家賃1万円(光熱水費別)で専用住宅に入居できる仕組みです。
移住後の数ある固定費のなかでも、家賃は大きな割合を占めるもの。専用住宅への入居が叶えば、出費を大きく削減しつつ、農家としての独立に専念できるでしょう。
和歌山県海南市
出典:海南市|わかやまLIFE
言わずと知れたみかんやびわの名産地、和歌山県海南市。1年を通じて温暖な地域であることから、農業が盛んです。特急列車の停車駅があり、大都市へのアクセスも◎なエリアとなっています。
和歌山県では農林水産就業補助金と呼ばれる、年間150万円を最大2年間交付する支援金制度を用意しています。県知事が認める研修機関等で、就農技術を習得するための研修を受ける、50歳未満の方が対象です。
石川県羽咋市
出典:羽咋市移住体験住宅のご案内|羽咋市移住定住ポータルサイト
石川県羽咋市(はくいし)は、日本海に面した海の見える町。
滝港マリーナや能登千里浜などレジャー拠点が豊富にあり、シーズン中は釣りやマリンスポーツが楽しめます。農耕も盛んな土地柄で、その営みは「能登の里山里海」として世界農業遺産にも登録済み。
羽咋市は空き家を利用した移住体験ツアーを実施しています。最大5日間まで宿泊でき、希望者は農業体験プログラムにも参加可能。
小旅行がてら、まずは一度訪れて見てはいかがでしょうか。
滋賀県長浜市
出典:新規就農 滋賀県で農業を仕事にしてみよう
滋賀県長浜市は、琵琶湖の北側にある歴史ある街。羽柴秀吉の時代に長浜城の城下町として栄えたのが有名で、日本最古の駅舎「旧長浜駅舎」など、歴史好きにはたまらないスポットがたくさんあります。
滋賀県は毎年100名ほどが新規に就農している、農業に力を入れている地域。
なかでも長浜市は、小規模農家営農継続支援事業補助金(小規模農家の、農業用機械の導入が最大30万円まで補助される制度)により小さな農家を保護し、個人でも就農しやすい街づくりを進めています。
宮崎県西都市
出典:農家民宿紹介|西都市観光協会
「日本のひなた」として知られる宮崎県は、年間平均気温が17度と温暖で、かつ降水量も九州一であることから、農作物がグングンと育つ土地。農家希望者におすすめの移住先です。
宮崎県のなかでも西都市は、農家民宿をはじめとする宿泊体験プログラムが充実しています。
野菜の種まきから野菜の出荷作業までできる農業体験などもあり、自分が移住して農家として働きはじめた後の姿も想像できるのではないでしょうか。


広島県江田島市
出典:広島県内の就農支援制度をご紹介します!【農業体験】|広島県
「憧れの島に移住して、農家として穏やかに暮らしたい」そんな方には、広島県の瀬戸内海側に位置する江田島市が向いています。
江田島市は島ながら広島本土にほど近く、一部の離島を除けば、「早瀬大橋」を使って車で簡単に行き来可能です。島暮らしながら不便すぎない、「利便性」と「自然に囲まれた暮らし」の両方の良いとこ取りができるエリア。
農業に関しては、先進農家のアドバイスを受けながら、研修ハウスで野菜の栽培研修受けられるほか、移住を前提とした新規就農者⽀援対策事業も実施中です。
まずは研修で、実際に働かれている農家の方の声を聞いてみてはいかがでしょうか?




「農業移住はうまくいかない」は本当?よくある失敗原因と対策


「農家としての移住は難しい」「農業に憧れて移住したけれど失敗した」という声を聞いたことのある方も多いのではないでしょうか?
実際のところ、農家としての移住に失敗する方が多いのは事実。
失敗の原因は大きく3つ考えらます。「こんなはずでは…」とならないよう、対処法とあわせてチェックしておきましょう。
原因①:農業の厳しさに対する認識不足
もっともありがちなのが、農業を甘く見てしまったケースです。
牧歌的なイメージこそあるものの、農業は重労働です。忙しいシーズンには休日がなかったり、日の出より前から日没まで働いたり、といったことも珍しくありません。重い肥料を抱えるなど、物理的な身体への負担もかかります。
単に憧れだけを抱えて移住するのではなく、ひとつの仕事として農業とはどのようなものなのか、しっかり理解しておく必要があります。
原因②:田舎暮らしや地域とのミスマッチ
大きめの田畑を求めて田舎に移住する場合、田舎暮らしに対する正しい認識を持つ必要もあります。
のどかな田舎に憧れる方は多いが、そこには田舎ならではの不便さもあるもの。電車やバスがほとんど走っていなかったり、最寄りのスーパーまで車で30分もかかったり。都会とはまったく異なる場所だと理解しておかなければなりません。
「郷に入っては郷に従え」という言葉があるように、自分からその土地に馴染もうとする努力も求められます。ときには、都会ではあり得ない慣習に驚くこともあるでしょう。
原因③:資金計画の甘さ
最後に注意しておきたいのが、見落としがちな金銭面についてです。
農業を生業とするのであれば、作物を育てて終わりではなく販売する必要があります。農協に加入するなど、自治体や先輩農家と相談しながら生計を立てていくことになりますが、いきなり高額な収入を得るのは難しいでしょう。
農家として軌道に乗るまでは、農業次世代人材投資資金など紹介した支援金が大きな助けとなります。
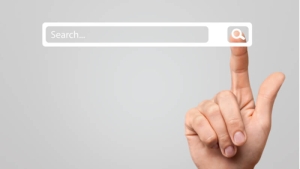
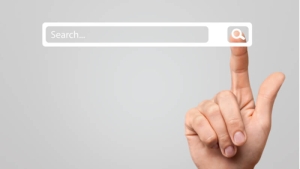
計画的な準備で、理想の農業移住を実現しよう!


失敗の声も多い農家としての移住ですが、正しく対処法を理解しておけば恐れるものではありません。地方創生が進むなか、支援金も充実している今が移住を実現する大チャンス。
まずは紹介した自治体と連絡を取り、農業体験やインターンシップに参加してみてください。
結果的にその地域に移住せずとも、実際に農業を行ってみることは、今後の役に立つ得がたい経験になるでしょう。