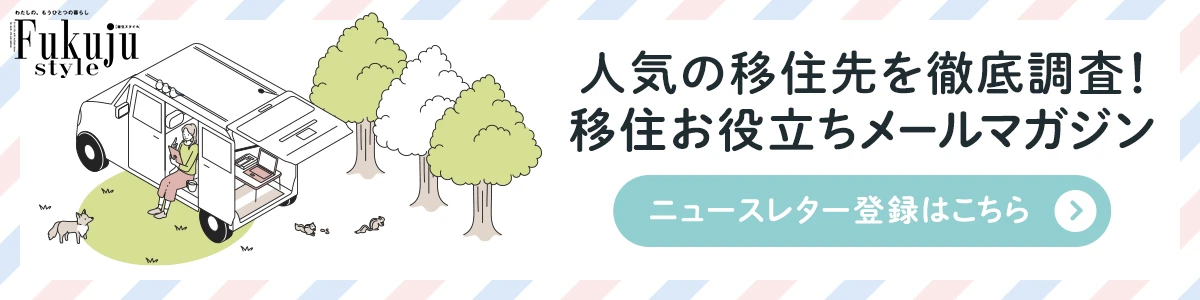毎年9月1日は防災の日。災害大国日本で暮らす私たちにとって、この一日はとても重要な意味を持ちます。地震や水害など、自然の恐怖と隣り合わせな日々を過ごす中で、今できる備えは何でしょうか?
この記事では、今すぐ始められる防災対策リストと、災害の少ない県をランキング形式で紹介します。
防災の日(9月1日)とは?今さら聞けない由来と歴史
「防災の日」は、昭和35(1960)年に制定されました。9月1日が関東大震災の発生日であるとともに、台風のシーズンとも重なること、そして、制定の前年にあたる昭和34(1959)年9月26日の伊勢湾台風によって、戦後最大の被害が出たことに由来します。
多くの自然災害を受け、地震や風水害などに対する心構えを育成するため、防災の日が創設されたのです。
関東大震災に学ぶ教訓
大正12(1923)年9月1日11時58分。相模トラフを震源としたマグニチュード7.9の大地震が発生。現在の墨田区や江東区で震度6弱以上を記録し、多数の死傷者や建物の損壊が出ました。これが「関東大震災」です。
被害の多くは”火災”によるものが多かったそう。昼食時に地震が発生したことで、調理に火を使用していた家庭がたくさんあり、建物の倒壊によってその火が同時多発的に燃え上がったといわれています。
また、神奈川県、静岡県、千葉県の海沿いを中心に、津波災害も発生。震源が陸地に近かったことで、地震発生からおよそ5分程で津波が襲ってきました。
こうした被害に対する復興事業として、公共施設やインフラを整備。建物の耐震性を強化したり、延焼を防ぐ効果のある公園や緑地を増設したりと、復興に向けて多くの取り組みが行われました。
防災週間で目指す減災のための備え
昭和57(1982)年からは、9月1日の防災の日を含む、毎年8月30日から9月5日までの一週間を「防災週間」と定めています。
防災思想普及のため、防災訓練や救命体験、防災ポスターの掲示や防災モーターショーなど、広い地域でイベントを企画・実施。大人から子供まで、多くの国民が災害に向き合い、防災の意識を高める期間となっています。
「防災」には、「災害を未然に防止する」だけでなく、「災害が発生した際に、被害の拡大を防ぎ、復旧を図る」という意味も含まれています。自然を操ることはできないため、災害が起こったときに最適な行動ができるよう、準備をしておくことが大切です。
防災の日(9月1日)と津波防災の日(11月5日)の違いは?


関東大震災を受けて制定された「防災の日」とは別に、毎年11月5日が「津波防災の日」と指定されています。
これは、平成23(2011)年3月11日14時46分に起こった東日本大震災において、東北地方の太平洋沿岸を襲った津波により多くの人命が失われたことをきっかけとしています。津波対策を総合的かつ効果的に推進することを目的に「津波対策の推進に関する法律」が制定され、その一環として、国民の間に広く津波対策についての理解と関心を深めるために「津波防災の日」ができました。
そのため、「防災の日」は自然災害全般を、「津波防災の日」は津波に特化した防災意識啓発を目的としています。
なお、11月5日は、安政元年11月5日(太陽暦で1854年12月24日)に起こった、安政南海地震の発生日です。この時、紀州藩広村(現在の和歌山県広川町)を津波が襲いましたが、濱口梧陵という方が稲むらに火をつけ、村人を安全な場所に誘導した伝承があります。このエピソードは「稲むらの火」として現代にも受け継がれ、防災意識の一助となっているのです。
防災の日に見直したい!防災対策リスト5選


小さなことからコツコツと!今からでもすぐに始められる5つの防災対策を紹介します。ご自宅でまだ実施していないものがあれば、ぜひ取り入れてみてください。
家具の固定で転倒防止
近年の地震による負傷者の30~50%は、家具類の転倒・落下・移動が原因だそうです。そこで、家具をしっかり固定し、けがを防ぎながら、逃げ道を確保できるように対策しておきましょう。
対策のポイント
- ネジ止め/突っ張り棒/粘着マットの活用
- キャスター付きの家具はロックしておく
- テーブルやイスにも滑り止め
- 避難経路が確保できるレイアウトにする
まずはとにかく家具の固定です。壁にL型金具でネジ止めをしたり、難しい場合には突っ張り棒を使用しましょう。さらに粘着マットをプラスすると効果がより高まります。
キャスター付きの家具があれば、移動させる時以外は必ずロックをかける癖をつけましょう。テーブルやイスの固定も忘れがちですが、足元にしっかり滑り止めを付けておくと安心です。
また、そうした家具の配置を避難経路に基づいて考えることも重要。ドアの近くに大型の家具を置いたり、火元の側に木製品を置いたりしないよう、安全に注意をしながら考えてみましょう。
防災グッズ・防災用品と持ち出し袋を用意
非常時に最低限の装備を持ってすぐに避難できるよう、持ち出し袋の準備はしっかりしておきましょう。持ち出し袋の中に入れておくべき防災グッズ・防災用品は以下の通り。
- 飲料水(1日1人3リットル×3日分が目安)
- 食料(人数×3日分が目安)
- モバイルバッテリー
- 簡易トイレ
- ホイッスル
- ビニール袋
- 防寒具/アルミブランケット
- 携帯ラジオ
- 運動靴/スリッパ
- 軍手
- 救急セット(絆創膏や包帯、常備薬など)
- タオル
- 筆記用具(メモ帳とペン)
- 懐中電灯
- 携帯用カイロ
- 衣類
- 雨具
- 現金
重さの目安は、男性15kg、女性10kg。両手が使えるリュックサックが適しています。また、背負ったまま問題なく動き回れることを事前に確認しておきましょう。
食料・水・医薬品の備蓄計画
大きな災害が発生すると、被災した地域ではスーパーやコンビニが営業休止となったり、道路の破損で物流の停滞が起こったりします。停電や断水の発生も考えられるため、自宅が無事であっても、備蓄がなければ生活を続けるのは難しいでしょう。
こうした事態に備え、食料や飲料水は最低3日分の用意があると安心です。また、家具が崩れた時に解体できる工具セットや、けがをした時に使用できる消毒液やマスク、明かりをとるための懐中電灯やろうそくなどを準備しておきましょう。
備蓄計画は、持ち出し袋とは違い、大きめサイズ・重めでもしっかり量を確保することがポイントです。
避難場所・安否確認手段の相談
災害時に家族全員が同じ場所にいるとは限りません。そこで、家族共通の避難場所を決めておきましょう。自宅近くの学校や役所など、災害時に避難所として地域に開かれる施設から選んでみてください。自宅の近隣で災害に遭った場合には、避難所で家族と合流できるようになります。
反対に、自宅から遠い場所で家族がバラバラに被災してしまった場合には、安否確認が必要となります。しかし、多くの人がインターネットや電話回線を使用することでパンクし、メールや電話が繋がりにくい状況が生まれてしまいます。
この時活用できるのが、「災害用伝言ダイヤル(171)」。被災地内の電話番号に限り利用可能なサービスで、安否情報の伝言などを音声で録音することができます。音声ガイダンスに従って操作するだけで、被災者からも、その家族や友人からも、双方が全国どこからでも伝言を再生・録音できます。1伝言あたり30秒以内の録音となるため、必要な情報をまとめておくと、焦ることなく利用できるでしょう。
さらに、携帯電話のインターネットサービスを利用した「災害用伝言板」も活用できます。被災者が自らの安否を文字情報によって登録することができるサービスです。災害発生時には、携帯電話各社のポータルサイトにリンクが表示され、そこから伝言を打ち込むことができます。登録された伝言は携帯電話やパソコンなどからサイトにアクセスし、登録者の電話番号を検索することで閲覧が可能。
こうした災害用の安否確認サービスを覚えておき、家族とも情報を共有しておくことが大切です。
感震ブレーカーの設置
大地震発生時、二次被害として起こりやすい火災。この発火源の50%以上は電気が原因といわれています。そこで使用をおすすめしたいのが「感震ブレーカー」です。
感震ブレーカーは、自宅のブレーカーに取り付ける防災アイテム。地震を感知すると自動的にブレーカーのスイッチを切ってくれるので、漏電や通電火災を防ぐことができます。
分電盤内蔵タイプや後付けタイプ、コンセントタイプから簡易タイプまで、さまざまなものが販売中。自治体によっては設置に関する助成を行っている場所もあるので、ご自身の環境に合うものを検討してみてください。
災害の少ない都道府県はどこ?【安全度ランキング】


総務省統計局による「都道府県別自然災害被害状況(令和4年)」をもとに、罹災件数や被害件数の少ない順にランキング。上位トップ5を都道府県別にご紹介します。
第1位:鳥取県
令和4年度の自然災害による鳥取県の被害は、7名の負傷者が発生したのみでした。
鳥取県では、県独自の危機管理ホームページを運営しており、緊急情報から防災知識まで幅広く発信しています。防災情報ポータルでは、気象注意報や土砂災害警戒情報、雨量情報や交通情報なども積極的に伝えているので、災害の不安がある時には覗いてみると安心です。
さらに、鳥取県独自の簡易手法で全県的の洪水リスクを評価。洪水浸水リスク図として情報提供を行っているため、移住先や二拠点先を選ぶ際には要チェックです。
第2位:山梨県
山梨県の令和4年度の自然災害による被害数は、死者・行方不明者1名、負傷者5名、床下浸水4件でした。
山梨県の危機管理課が発表する災害リスク資料によると、直近50年の間に発生した⼭梨県を震源とする震度4以上の地震は「⼭梨県東部地震」(震度4)のみ。災害の発生件数が少ないことが分かります。
ただし、昭和町を中心とした県中央部に地震や浸水被害の危険が示されていることや、台風被害の発生率が高いことに注意が必要です。
第3位:茨城県
茨城県では、令和4年度の自然災害により、1世帯・2名が罹災、負傷者9名、床上浸水1件、床下浸水4件が発生しました。
茨城県には火山も無く、台風や異常気象も少ないことから、水害や土砂災害などのリスクも低い傾向にあります。
しかし同時に、茨城県は地震の発生率が高い県としても有名です。これまでは、震源地が深く、地表面では大きな震度を観測することはありませんでしたが、今後30年以内に災害リスクが高まる傾向があるそうです。
首都直下型地震や南海トラフ地震の予測影響もあり、茨城県でも今後30年以内に震度6弱以上の激しい揺れに襲われる確率が高まっています。水戸市で81%と予想されるなど、警戒は必要でしょう。
第4位:和歌山県/徳島県
令和4年度の自然災害では、和歌山県では1世帯・1名が罹災、負傷者5名、床上浸水1件、床下浸水6件、河川氾濫4件が発生。徳島県では、負傷者8名と河川氾濫10件が発生しました。
和歌山県も徳島県も、地震、豪雨ともに発生件数が少ない県として知られています。現状、どちらの県も南海トラフ地震の被害地域に想定されますが、事前に予測がされているからこそ、県はフォローアップ体制を強化中。
和歌山県では、「被災者支援」や「インフラ」といった5つのテーマ別に、110項目の取り組みを行うと決定しました。徳島県でも、南海トラフ巨大地震に係る「新たな防災対応」の推進及び、大規模地震を迎え撃つ「事前防災・減災対策」の推進。自治体が被害を最小限に食い止めようと取り組んでいます。
第5位:香川県/佐賀県
令和4年度の自然災害による被害状況を見ると、香川県では3世帯・5名が罹災、負傷者2名、床上浸水3件、床下浸水8件、河川氾濫4件が発生。佐賀県では、1世帯・1名が罹災、死者・行方不明者1名、負傷者4名、建物半壊1件、床下浸水2件、河川氾濫15件が記録されています。
香川県は、自然災害被害額が全国5位の少なさ。暮らしの安心感が移住理由の上位にも挙がるほどです。一年を通して気候が温暖なため、年間降水量も少なく、台風や豪雨被害が少ないという特徴があります。
佐賀県も自然災害が少ないといわれている県のひとつ。明治以降、地震による死者はなく、南海トラフ地震の予測でも、九州で唯一津波が想定されていません。
防災の日だからこそ、”いつか”ではなく”今”向き合う災害対策
日本では地震や台風、豪雨、火山噴火など、自然災害がいつ発生するかわかりません。だからこそ、過去の災害に向き合い、その教訓を学ぶ必要があります。
時には、災害リスクの少ない県に移住したり、二拠点目を確保することで、安全で安心な暮らしを手に入れることができるかもしれません。防災意識を高め、次の世代へと繋げていく取り組みを続けていきましょう。